あるがまま
「自分は正しい(あるがままでよい)のだ」と人前において堂々と表現することはもとより、ただそう思考することでさえ許せなかったり気分が悪くなってしまうようにプロテクトがかけられているのは、強烈な罪悪感の刷り込みによるものです。
たとえ上辺だけ逆さを気取って「オレ様は正しいんだ!」と叫んでみても、そうではないと思っていることの裏返しに過ぎません。確信があることを強調する必要はないからです。
子供の頃より両親や社会などから「お互いに無力であることによる安心感を維持することが調和である」とする倫理、礼儀、常識の教育を受け、それらを規範とした相互監視と足の引っ張り合い(自らも参加)を生活の基本としてきたので、萎縮しない態度は傲慢であるとして切り捨てられてきました。
ただし親には悪意があったわけではなく、彼らも同じような事情を抱えていましたし、社会でうまく泳いでいくための知恵として授けられたものは意図通り機能してきた面もあります。
確かにある程度の時間的精神的な準備段階を経ずに飛び出してしまうと、思いが空回りしたまま世間から異端として虐げられることに耐えきれず、厭世観のみを残して目的半ばで挫折してしまうかもしれません。
自由への旅を決意すると、(これまで自分も所属していた)恐怖と不自由を信念とするチームが、脅したり宥めたりしながら立ちはだかってくることは避けられないでしょう。 そこにはエゴ特有の「新しいことは今より悪くなるはずだ」という怖れがベースにあります。さらには「自分が選択する」のではなく、常に誰かや何かに「やられる」とか「されるのだ」という被害意識と不信感が支配的です。 溺れた状態(浮かばないまでも沈まないだけましである)を維持することが平和であるとする集団合意に疑問を持ったり異議を唱えるということは、安眠を妨害し変化を要求する(つまり攻撃してくる)危険人物としての意味合いを持つことになります。
余計なことはせずに、みんなと同じ古巣に戻ってくるようにと強力に誘惑されますが、彼らの存在とは自分の一面が「世界」に反映されたものだと言えます。 進みたい気持ちと引き返したい気持ちの両方のエネルギーが相克していることを説明するものなので、外側と直接格闘したり誰かを非難しても問題は解決しません。自らの内面を癒すことによって「世界」は同調します。
エゴの視野からすれば自分に敵対しているように見えるものでも、邪魔をしているとしか理解できないものであっても、宇宙のもたらす真実は常に「良かれ」が基本になっています。鍛える力が弱い刀鍛冶では、良い刀は生まれません。 そうは言っても現場ではなかなか理屈通りには受け入れられなかったり、怒りや憎しみで一杯になって何も信じられなくなることもあります。
いっそのこと「やられてしまったんだ」と思い込むことによって、無力無責任な立場に身を置いてしまえば楽になれるような気もします。 これらの過程は光に至るための一つの通過儀礼として現れるものです。
サタンや魔羅としても表現されるこの葛藤を乗り越えることによって、正しいということの本当の意味、悪の反対側ではなくて、自然のあるがままで何も問題はないのだという理解が生まれてきます。

「神」なるものを肉眼では見たことがないし見ることもできないのを理由に、その存在を疑ったり表面上無視することは出来ますが、同じ理由で完全に否定することも不可能になっています。 「神は有るのか?無いのか?」で論だけを重ねても、それ以前に自分がなぜ存在しているのかさえ分からないのならば、結局ハッタリ以上の結論は得られません。理屈の調整だけでは救いとはならず、次の理屈を延々と生み出すだけで終わりとなります。
「世界」を見渡したときに、真面目な顔で「神」の話をしている人の数は数千数万人のレベルではなく、宗教人口だけでも億単位であり、長い歴史を踏まえています。 為政者のエゴに利用されてきた経緯があるとしても、もし火のないところに生まれた煙ならば、説明がつかない程の量だとも言えます。
確かに「神」に関連する胡散臭かったり生臭い例を探し求めればいくらでも見つかりますし、ここを含めてかなり飛んでしまっているようなものはありますが、全ての全てが頭のイカレている人ばかりだと言い切るのにも無理があるようです。
無神論の人が必ずしも自信と幸せに満ちた徳のある人物であるとは限らず、また神を信じながらも本当に愛を表現しているように見える人もいます。 ただヒステリックに「嘘だヤラセだ、何が何でも信じないぞ」では、「何が何でも信じるぞ」と盲信するのと同じことになってしまうので、問題が問題なだけに白黒はっきりつけたいところです。
鵜呑みにしないまでも完璧に反駁するだけの材料もなく、この問題に対して肉体寿命の範囲内で有耶無耶を続ける選択肢はあるにせよ、最終的な責任が自分にやって来るだろうという結論は避けられません。
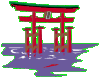
普段は信仰や宗教的な関わりを持たず、神のことなど滅多に気にとめることのない人であっても、形式的であれ盆正月や冠婚葬祭、観光地等で、(神を説明しているとされる)神社仏閣教会にお参りすることはあるでしょう。
「神」に関して社会一般に流布されているようなストーリーならば誰でも知っていますし、その多くは勧善懲悪的なものがベースになっていることがわかります。 これら「常識」による価値判断の呪縛にとらわれていれば、神に対する潜在的な畏怖の念や罪悪感のようなものを払拭することは難しくなります。
神とは善を司り悪を裁き懲らしめる存在だと言われても、「善悪」の定義は曖昧のままなので、ファンクラブ同士がそれぞれの「神」の代理としての言い分を元にして、血を流すような争いを引き起こすこともあります。
この場合の「言い分」とはすなわちエゴのことです。神の定義する善悪ではなく、自分の欲得に最適化させた定義に過ぎないというのは、少しでも内面を振り返ればわかることですが(わかってしまうことなので)、そこは思考停止の力業で振り切ってしまいます。
外部に見つかる「いわゆる神」に関する情報を検討した場合、たとえば現世で好き勝手に暴れて死んだ後に「あれ?やっぱり神がいた。裁かれてしまった!」となっては大変なことだと理解できます。 自暴自棄のフリやごまかしが通用するのも生きている間だけだとすれば、「あれはほんの冗談のつもりだったんです」で済むレベルでもなさそうです。地獄に堕ちたり舌を抜かれてはかないません。これが丁か半かのリスク上にあるわけです。
人が罪悪感に翻弄され、無意識に天罰を怖れたり謝罪行為に励もうとする方向の奥底には、存在するかもしれない「神」に監視採点されている可能性に対する根源的な恐怖があります。
これは想像されるよりも大きな影響を、日常生活の節々から人生全体にまでに及ぼしていると言えます。そして恐怖は自他分離と争いのドラマを生み出していきます。
実際には死後に「どこか」に行ったり、白髭のお爺さん的な神や閻魔大王が現れて裁いたりすることはありませんが、自らの力で本当の神を見つけるまではこれらの不安から抜け出すことは困難でしょう。
その時ごとの誰か「神を知ってそうな人」の言い分に翻弄されながら、妄想に脅迫されながら、細く不安定な板の上を渡り歩いていくことになります。
神に裁かれるなど「されること」として想像するものは、自分が自他に対して「していること」を指しています。つまり自分を説明するものであって、神を説明するものではありません。
「神は存在するはずだ」とか「いや存在しないだろう」と言っているのは「誰」なのかを問うことによって幻想を整理し不安を消し去る方向を見つけられます。
→次へ |