| わたしは「見ている」のか「見せられている」のか。
◆そこにあるもの
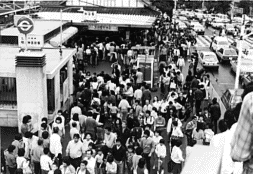 街の中にはさまざまな人や物が存在しているように見えます。 街の中にはさまざまな人や物が存在しているように見えます。
色とりどりの格好をした老若男女、にこやかな人不機嫌な人、親切な人不親切な人、幸せな人や不幸せな人が歩いている。
店先には無数の品物が陳列され、壁や電柱には看板やポスターなども貼ってあり、道端には花が咲いていたり、またはゴミが落ちているかもしれない。天気は晴れの日もあれば曇りや雨の日もある。車や動物も往来しています。
音や匂いも含めて刻々千変万化していく世界は、際限のない膨大な情報で溢れていると言えます。
たとえばある数百メートルの路地を歩いて抜けるのに10分ほどかかるとしたとき、その時間内でそこに存在する全ての人や物を同時に認識することは当然不可能なので、何かを見るときには、全体の中から瞬間瞬間に自分で見る対象物をどれか「選択」することになります。
どんなに五官を駆使し脳味噌をフル回転させても実際に認識出来るのは、そこにある「世界」全体のほんの僅かな部分に過ぎません。
大勢の中から選択したAさんという人を見ている間に、BさんやCさんはわたしの横や後ろを通り過ぎてしまうかもしれない。時間を巻き戻すことは出来ないので、通り過ぎてしまった(と想像することしかできない)BさんやCさんがどんな人だったのかは、もはや確認する術はないし、そう言っている今この瞬間にも新たな情報が次々と現れているので、想像に構っている余裕もないとも言えます。
その場合、わたしにとってその路地において得たところの現実、あるいは刻み込まれた歴史とは、「Aさんは存在し、BさんとCさんは存在していない」というものになります。
同じ時に同じ場所にいたとしても、Bさんを見ていた人にとってはBさんが現実なのでしょう。その場合には、Aさんは想像上の人物であり存在していない人です。もちろん人間だけではなく、あらゆるものに関しても同じことが言えます。
結果として僅かな部分情報が全体の印象を代表することになるので、一発勝負の選択がそこでの現実や体験を変えていきます。そしてこの結果の繰り返しが肉体の寿命の範囲で行われて、わたしのある一つの生のサイクルが創造されるのでしょう。
→次へ
|